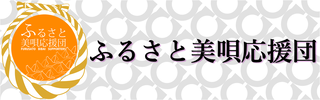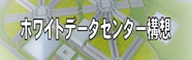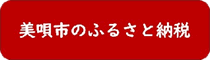本文
児童扶養手当
児童扶養手当について
児童扶養手当は、父または母のいない家庭、父または母が一定の障害の状態にある家庭の児童について、その児童の父または母、もしくは児童の両親に代わってその児童を養育している人(養育者)に支給される手当です。
支給を受けるためには審査があり、支給を希望する方および一緒にお住まいの方の個人情報(公的年金の加入状況や所得情報等)を確認したり、詳しくお話を伺う必要があるため、支給を希望する本人が窓口で直接相談・申請する必要があります。
1 児童扶養手当の受給資格(手当を受けることができる方)
次の1~9に該当する児童を養育する父または母、もしくは父母に代わって児童を養育している方が手当を受給できます。
ただし、受給資格者本人、配偶者、同居している扶養義務者(受給資格者の直系親族、兄弟姉妹)の所得などにより、支給制限があります。
なお、児童扶養手当制度でいう「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童をいいます。また、児童に国が定める程度の障がいがある場合は、20歳未満まで延長されます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいの状態(国民年金の障害等級1級相当)にある児童
- 父または母が死亡の原因となるべき危難に遭遇し生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父母ともに不明である児童
ただし、上記1~9に該当する場合であっても、次の(1)~(3)に該当する場合は、手当を受給することができません。
- 父または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき
※ 配偶者が重度の障がいの状態にある場合を除く - 対象児童が里親に委託されているとき または 福祉施設に入所しているとき
- 手当の受給資格者、対象児童の住所が日本国内にないとき
2 手当の支給制限(所得による制限)
手当の支給額は、受給資格者本人、配偶者、同居している扶養義務者(受給資格者の直系親族、兄弟姉妹)の前年中の所得等(注)に応じて「全部支給」、「一部支給」、「支給停止(支給額 0円)」のいずれかに決定されます。
(注)
- 1月~6月の間に、認定請求(新規手続き)をされる場合は、前々年中の所得等
- 児童扶養手当制度では、母または父及び児童が、前夫または前妻(児童の父または母)から受け取った養育費の8割が所得に算入されます。
- 所得からは所得税における次の諸控除と一律控除8万円が差し引かれます。
- 養育者・扶養義務者の所得に係る寡婦・寡婦控除のみなし適用につきましては、子の所得証明書(扶養親族その他のものと生計を一にする子の前年の総所得金額が38万円以下のもの)戸籍、申請書等が必要となります。
* 詳しくは、こども未来課まで
| 諸控除 | 控除額 | 諸控除 | 控除額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 障害者控除 | 27万円/人 |
小規模企業共済等掛金控除 |
この控除額 |
受給資格者が父または母の場合、父または母の所得からは、寡婦(夫)控除、特別寡婦控除を差し引かない |
| 特別障害者控除 | 40万円/人 | |||
| 勤労学生控除 | 27万円 | 配偶者特別控除 | この控除額 | |
| 雑損控除 | この控除額 | 寡婦(夫)控除 | 27万円 | |
| 医療費控除 | この控除額 | ひとり親控除 | 35万円 |
所得制限限度額表 (令和6年11月より)
|
扶養親族等の数 |
受給資格者本人の所得制限限度額 |
孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額(3) |
|
|---|---|---|---|
|
全部支給の限度額(1) |
一部支給の限度額(2) |
||
| 0人 | 69万円未満 | 208万円未満 | 236万円未満 |
| 1人 | 107万円未満 | 246万円未満 | 274万円未満 |
| 2人 | 145万円未満 | 284万円未満 | 312万円未満 |
| 3人 | 183万円未満 | 322万円未満 | 350万円未満 |
| 4人以上 | 4人以上の場合は、1人につき38万円を加算 | ||
|
扶養親族に老人控除対象配偶者を含むとき |
10万円を加算 |
10万円を加算 |
加算なし |
|
扶養親族に老人扶養親族を含むとき |
10万円/人を加算 | 10万円/人を加算 |
6万円/人を加算ただし、扶養親族の全員が老人扶養親族の場合は1人を除く |
|
扶養親族に特定扶養親族、16歳~18歳の控除対象扶養親族を含むとき |
15万円/人を加算 | 15万円/人を加算 | 加算なし |
「全部支給」「一部支給」「支給停止」の区分
| 受給資格者本人、配偶者、扶養義務者の所得 | 区分 |
|---|---|
|
受給資格者本人の所得が所得制限限度額表の(1)未満で、かつ、配偶者、扶養義務者の所得が(3)未満のとき |
全部支給 |
|
受給資格者本人の所得は所得制限限度額表の(1)未満だが、配偶者、扶養義務者の所得が(3)以上のとき |
支給停止 |
|
受給資格者本人の所得が所得制限限度額表の(1)以上(2)未満で、かつ、配偶者、扶養義務者の所得が(3)未満のとき |
一部支給 |
|
受給資格者本人の所得は所得制限限度額表の(1)以上(2)未満だが、配偶者、扶養義務者の所得が(3)以上のとき |
支給停止 |
| 受給資格者本人の所得が所得制限限度額表の(2)以上のとき | 支給停止 |
*所得制限限度額の算定は、30歳以上70歳未満の扶養親族のうち所得税法に規定する控除対象扶養親族でないものについては除きます。(令和6年11月より適用)
*土地収用で土地を譲渡した場合に生じる売却益等については、児童扶養手当の支給制限のために所得を算定するに当たって、総所得金額等合計額から控除します。(上記につきましては、必要書類や適用要件がございます。窓口へお問い合わせください。)
*令和5年の所得から、所得税法(昭和40年法律第33号)上の扶養控除の取り扱いに関し、30歳以上70歳未満の控除対象扶養親族に係る国内居住要件が設けられましたが、児童扶養手当における所得制限限度額の算定においては、30歳以上70歳未満の扶養親族のうち所得税法に規定する控除対象扶養親族でないものについては除かれます。(令和6年11月より適用)
3 手当の支給制限(公的年金等の受給による制限)
受給資格者や対象児童が公的年金、遺族補償、業務災害、通勤災害を受給することができるとき(児童が子の加算対象になっている場合を含む)は、受給する公的年金等の額が、児童扶養手当の額よりも低い場合に、その差額分を児童扶養手当として支給します。
受給する公的年金等の額が、児童扶養手当の額よりも高い場合は、手当の全額が支給停止になります。(支給額 0円)
※公的年金等と児童扶養手当の差額支給については、様々なケースがありますので、詳細については、受給する公的年金等の額がわかる書類をご用意のうえ、児童扶養手当担当窓口へお問い合わせください。
4 手当の月額 《 令和7年4月改正 》
| 支給対象児童数 | 全部支給の月額 |
一部支給(所得による支給制限)の月額 |
|---|---|---|
| 1人目 |
46,690円 |
46,680円~11,010円 (10円単位) |
| 2人目以降 |
11,030円を加算 |
11,020円~5,520円を加算 (10円単位) |
一部支給(所得による支給制限)の計算式
- 支給対象児が1人の場合
月額 = 46,680円 - ( 受給資格者の所得-全部支給の所得制限限度額 )× 0.0256619 - 支給対象児が2人以上いる場合
加算額 = 11,020円 - ( 受給資格者の所得-全部支給の所得制限限度額 )× 0.0039568
※受給資格者や対象児童が公的年金等を受給することができるとき(児童が子の加算対象になっている場合を含む)は、上記の額から公的年金等の月額相当額を差し引いた額が、手当の月額になります。
(例)
|
所得により算出した児童扶養手当の額 |
月額45,500円 |
|---|---|
| 受給している公的年金の額 | 月額25,000円 ( 年額300,000円/12月 ) |
| 支給する児童扶養手当の額 | 月額45,500円-25,000円=20,500円 |
5 手当の支給日
| 手当の支給日 | 支給対象月 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 年6回 | 1月11日 | 11月~12月分を支給 |
|
| 3月11日 | 1月~2月分を支給 | ||
| 5月11日 | 3月~4月分を支給 | ||
| 7月11日 | 5月~6月分を支給 | ||
| 9月11日 | 7月~8月分を支給 | ||
| 11月11日 | 9月~10月分を支給 | ||
6 手当の認定請求(新たに手当を受けるための手続き)
新たに手当を受けるためには、認定請求が必要です。認定請求は、下記の受付窓口で事前相談のうえ行っていただきます。手当の支給が認定されると、認定請求を行った月の翌月分の手当から支給になります。
手当の認定請求に必要なもの
- 受給資格者と対象児童の戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)
※離婚の直後で戸籍の作成に日数を要する場合は「離婚届受理証明」の提出により手続きを行うこともできます。
ただし、戸籍作成後、直ちに全部事項証明書(戸籍謄本)を提出していただきます。 - 受給資格者、配偶者、扶養義務者が次に該当する方は、児童扶養手当用の所得証明書
1月~6月までの間に認定請求する場合で、前年の1月2日以降に美唄市に転入された方
7月~12月までの間に認定請求する場合で、本年の1月2日以降に美唄市に転入された方
※所得証明書は、1月1日時点で住民登録をされていた市区町村で発行されます。 - 受給資格者、対象児童、配偶者、同居している扶養義務者の個人番号カードまたは通知カード
(受給資格者の直系親族、兄弟姉妹) - 印鑑
- 受給資格者本人名義の預金通帳 ※手当の振込先口座
- 申請理由などにより改めて書類等が必要となる場合があります。
手当の認定審査のため確認させていただくもの
- 受給資格者の年金手帳
- 受給資格者及び対象児童の健康保険証
- 必要に応じてその他書類等を確認させていただく場合があります。
受付窓口
美唄市子育て支援センターはみんぐ
美唄市西3条南2丁目4番1号(市役所の南側隣り)
こども未来課 Tel0126-62-3147