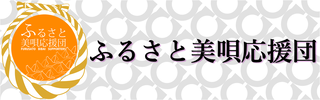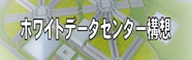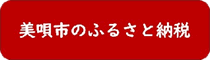本文
犬と猫の飼育マナーについて
記事ID:0000835
更新日:2023年12月6日更新
飼主の社会に対する責任
飼い主もペットも地域社会のルールの中で暮らしている以上、自分勝手な行動は許されません。ぺットが嫌われる理由のほとんどは、動物によるものではなく、飼い主のマナーが悪いことが原因です。
地域社会の中には、動物が嫌いな人や恐怖心を持っている人、動物に対しアレルギーを持つ人もいます。放し飼いは、ペットの飛び出しによる交通事故や咬みつき事故等、人も動物も怪我をする危険があります。
公共の場所や個人の敷地に排泄物が放置されているのは誰にとっても不快なだけでなく、衛生上も問題があります。また、飼い主が気付いていてなくても、鳴き声や毛の飛散、排泄物の匂いなどを迷惑に感じている人もいます。日頃から周囲への人々への配慮が必要です。
犬の飼い方のルールやマナーについて
- 犬の登録と狂犬病予防注射
狂犬病予防法により生後91日以上の犬には登録と狂犬病予防の接種、鑑札と注射済票の装着が義務付けられています。 - 放し飼いや散歩で放すことの禁止
柵に囲まれた自己の敷地内や屋内で飼う場合以外は、放し飼いをしてはいけません。 - つないで飼う場合は場所と綱の長さに気を配る
人に危害を与える恐れのないように注意しましょう。 - 周辺地域の住民や環境への配慮
鳴き声や毛の飛散、排泄物の放置などで地域に迷惑をかけてはいけません。トイレは散歩の前に自宅内でするようにしつけましょう。 - 散歩のときの安全確保とふん尿の処置
散歩は必ずリードを付け、犬を制御できる人が行い、時間帯や場所に配慮しなくてはなりません。長すぎるリードでの散歩は、犬にも人にも危険です。また、飼い犬のふんや尿の後始末は、飼い主の責任であり最低限のマナーです。犬を散歩に連れて行くときは、ビニール袋などを持って行き、ふんは必ず持ち帰り、尿は水をペットボトルなどに携帯し流しましょう。 - 適正なしつけ
社会に受け入れられるようなしつけをし、特に制止(マテ)ができるようにしなくてはなりません。また、呼び戻し(オイデ)ができると、いざというときに役立ちます。 - 飼い犬の性質や特性を知る
飼い犬の性質や特性をよく理解し、事故をおこさないよう注意するとともに、病気の知識と予防に努め、その命を終えるまで適切に飼うようにしなくてはなりません。
猫の飼い方のルールやマナー
- 猫は室内で飼いましょう
屋外には危険がいっぱいです。感染症や交通事故、迷子や予期せぬ繁殖、近所からの糞尿被害や花壇や畑を荒らすなどの苦情や相談が多くあります。また、たとえ室内飼いであっても、空いた窓やドアからの脱走があるので、飼い猫と分かるように首輪や迷子札をつけましょう。 - 不妊去勢手術
子猫が生まれることを望まない場合や、生まれた子猫をすべて幸せに出来ない場合は、不妊、去勢手術をしましょう。病気の予防やストレスの軽減になるとともに、オスの場合は去勢手術をすることにより、あちこちに尿をかけるスプレー行動の予防にもなります。 - 猫についてのご相談は、空知総合振興局保険環境部環境生活課 0126-20-0045 まで
動物を飼う前に
北海道ホームページ 動物を飼う前に<外部リンク>
環境省ホームページ
環境省ホームページ(動物の愛護と適切な管理)<外部リンク>