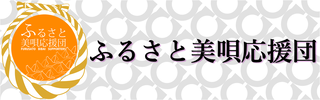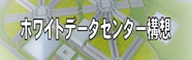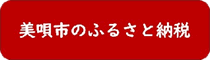本文
国民健康保険税について
納税義務者
国民健康保険税は、世帯を単位とするため、世帯主が納税義務者となります。
そのため、国民健康保険税の納税通知書は、世帯主宛に送付します。
世帯主が国民健康保険の被保険者ではない場合も、世帯内に国民健康保険の被保険者がいる場合は、世帯主宛に納税通知書を送付します。
【よくあるご質問】国民健康保険税の納税義務者は?
計算方法
国民健康保険税は、「医療保険分(医療分)」・「後期高齢者支援金分(支援分)」・「介護保険分(介護分)」の3つの区分ごとに計算し、その合計額が年税額となります。
|
40歳未満の方 |
医療分+支援分 |
|---|---|
| 40歳~64歳の方 | 医療分+支援分+介護分 |
| 65歳~74歳の方 | 医療分+支援分 |
※医療分:国保被保険者の医療給付費等に充てられ、すべての国保被保険者が対象となります。
※支援分:後期高齢者医療制度被保険者の医療給付費の一部に充てられ、すべての国保被保険者が対象となります。
※介護分:介護納付金の納付に充てられ、40歳から64歳までの国保被保険者が対象となります。
年間の税額(令和7年度)
| 年税額 | = |
所得割 |
+ |
均等割 |
+ | 平等割 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医療分 |
課税所得金額 ×8.9% |
加入者数 ×28,500円 |
26,000円 | |||
| 支援分 |
課税所得金額 ×3.2% |
加入者数 ×9,000円 |
8,100円 | |||
| 介護分 |
課税所得金額 ×2.0% |
加入者数 ×9,700円 |
6,500円 |
※賦課限度額(課税の上限額)は、医療分66万円、支援分26万円、介護分17万円
- 所得割:世帯の国保被保険者の前年中の所得をもとに計算
- 均等割:世帯の国保被保険者数をもとに計算
- 平等割:一世帯あたりの計算
よくあるご質問
軽減制度
前年中の世帯の所得が一定基準額以下の場合、国民健康保険税のうち「均等割額」と「平等割額」を軽減する制度があります。
また、軽減の判定には、世帯主が国保被保険者であるなしにかかわらず、世帯主の所得も世帯の所得額に含まれます。
なお、未就学児の均等割額は5割軽減されますが、この場合、世帯で軽減が適用された後に、未就学児の均等割額を軽減します。
| 区分 | 世帯内の総所得金額の合計 |
|---|---|
| 7割軽減 | 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与・年金所得者数-1)以下 |
| 5割軽減 | 基礎控除額(43万円)+30.5万円×(被保険者※数)+10万円×(給与・年金所得者数-1)以下 |
| 2割軽減 | 基礎控除額(43万円)+56.0万円×(被保険者※数)+10万円×(給与・年金所得者数-1)以下 |
※国保被保険者には、同じ世帯で国民健康保険制度から後期高齢者医療制度に移行した方も含みます。
なお、昨年の収入を申告されていない世帯に関しましては、軽減措置が受けられない可能性があるため、必ず収入申告をしてください。
【よくあるご質問】 申告せずにいたら、国民健康保険税が高くなったのはなぜ?
納期
国民健康保険税は、毎年7月に決定し、4月から翌年3月までの1年分を7月から翌年2月までの8回にわけて納付していただきます。
(加入月と支払月は必ずしも一致しませんので、ご注意ください。)
【よくあるご質問】 国民健康保険税の支払時期は?
※国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯につきましては、原則として世帯主の年金から特別徴収(天引き)による納付になります。
(年金特別徴収対象の方でも、申し出により、口座振替への変更が可能です。)
ただし、以下の1~3のいずれかに該当する場合は、年金特別徴収は実施されません。
- 世帯主が国保被保険者以外の場合
- 年金が年額18万円未満の場合
- 介護保険料と国民健康保険税を合わせた年金特別徴収額が年金額の2分の1を超える場合
納めるのが困難なとき
災害など特別な事情があると認められたときは、国民健康保険税の減免や徴収の猶予を受けられることがあります。納付が難しいときは、そのままにせず、市役所1階市税窓口に相談してください。
詳細は「納税相談と分割納付」、「市税及び保険料の減免について」のページをご覧ください。