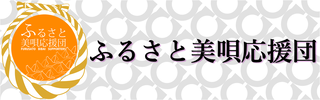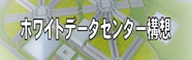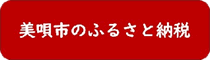本文
補装具について
身体障害者手帳の交付を受けた方、並びに難病患者等がその障がいを補うための用具(補装具)としての交付・借受け・修理が必要と認められたときに費用の一部を助成します。補装具の種類によっては、交付・借受けの際に北海道立心身障害者総合相談所の判定が必要になる場合があります。
補装具は購入する前に申請をしないと、給付できませんので事前に市役所の地域福祉係へご相談ください。
損害賠償制度、業務災害補償制度、社会保険制度など他制度が優先となりますので、これらの他制度に該当する方は各制度の保険者までお問い合わせください。
原則、費用の1割が自己負担となりますが、所得に応じて負担上限額が設定されています。ただし、用具ごとに公費負担の基準額が設定されており、基準額を超過した差額につきましては全額自己負担となります。
治療やリハビリのために使用される装具等(訓練用義足、歩行訓練用短下肢装具、患部変形の矯正用装具など)は、医療保険による給付となることや日常生活用でないため対象となりません。
18歳以上の場合は、障がい者本人または配偶者が一定所得以上(当年度の市民税所得割額が46万円以上)の方がいるときは対象外となります。
※R6年4月1日から18歳未満の利用者に係る上記市民税所得割額の制限が撤廃されています。
補装具の種類
・ 義肢
・ 装具
・ 姿勢保持装置
・ 補聴器
・ 車椅子
・ 電動車椅子
・ 重度障害者用意思伝達装置
・ 視覚障害者安全つえ
・ 義眼
・ 眼鏡
・ 歩行器
・ 歩行補助つえ
18歳未満の障害児及び18歳未満の難病患者等のみ
・ 車載用姿勢保持装置
・ 起立保持具
・ 頭部保持具
・ 排便補助具
判定の有無
原則18歳未満の障害児の判定は不要です。
18歳以上の障がい者は補装具の種類によって北海道立心身障害者総合相談所の判定(文書判定・直接判定)が必要となります。
申請に必要なもの
1 身体障害者手帳(難病患者等の場合は、医師の意見書または病名と状態がわかる書類)
2 補装具費支給意見書(医師が記載)
3 補装具の見積書(意見書に基づき補装具業者が作成したもの)
4 印鑑
5 個人番号(マイナンバー)がわかるもの