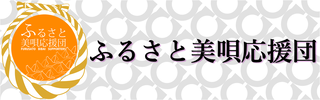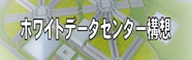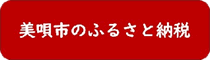本文
美唄市小学校農業科読本について
美唄市小学校農業科読本―地域に根ざし、暮らしに学ぶ―
 本市では、基幹産業である農業の教育的効果に着目し、農業の持つ力を、次代を担う子どもたちに伝えていきたいとの思いで、平成22年度から「小学校農業体験学習」をスタートさせ、学習の手本となる「小学校農業体験学習副読本」を作成し、小学校の授業で使用してきました。
本市では、基幹産業である農業の教育的効果に着目し、農業の持つ力を、次代を担う子どもたちに伝えていきたいとの思いで、平成22年度から「小学校農業体験学習」をスタートさせ、学習の手本となる「小学校農業体験学習副読本」を作成し、小学校の授業で使用してきました。
道内では前例のない「農業体験学習副読本」を美唄市が作成することになったのは、福島県喜多方市が先鞭をつけた先駆的な取組を知ったのが契機であり、現在も道内179自治体の中で「副読本」を持っているのは、美唄市が唯一の自治体です。
福島県喜多方市は、平成19年に日本で初めて、小学校の授業に「農業科」を組み入れ、今なお、取組を継続しており、そのきっかけとなったのは、日本の生命科学の第一人者であり、JT生命誌研究館を創設された中村桂子名誉館長が「人間は生きものであり、自然の一部」という事実をもとに、「未来を担う子どもたちが、生きることの本質を学ぶ機会として、“小学校で農業を必須に”」と提唱されていたことが端緒でした。
中村桂子さんは「経済社会の動きを知るための“株“の勉強より、子どもたちは、大地に育つ“カブ”から学ぶことの方が大事」と語り続けてこられました。そうした中村桂子さんの未来を見据えた熱い言葉に共感・共鳴した当時の「喜多方市長」が、その思いを具体化し、日本で初めて小学校教育に「農業科」を組み入れることとなりました。
その中村桂子さんと美唄市とのご縁は、令和4年8月、安田侃彫刻美術館アルテピアッツァ美唄で開催した「アルテピアッツァ美唄30年・”次なるステップへ”事業」で講演いただき、中村桂子さんからは、「全国で広く一般的に行われている農業の“体験学習“は、あくまで一過性の“体験”の域にとどまるが、学校の授業の「時間割」の中に、“農業“として明記されていることが何より大事、国語、算数、理科、社会と同じように記載されていることで、子どもたちの心にしっかり“農業”への思いが刻まれ、未来につながることになる」というアドバイスをいただきました。

この度、「副読本」の発行後13年が経過したことから、改訂版づくりに取り組み、中村桂子さんからの、次の時代を見据えた的確なアドバイスを踏まえ、今年度から、小学校の授業の時間割の中に「農業科」を組み込み、継続的に「農業で学ぶ」取り組みを進めていくこととしました。
そして、これまでの「副読本」についても「副」を取り、「小学校農業科“読本“」と改め、「農業科」の授業を進めていく手立てとしての役割をより明確な形にして発行いたしました。
地球環境が困難な時代を迎えている今、「農業で学ぶ」ことで、生きものとしての人間が、生きる仲間たちの生命をいただくことで支えられていることを深く認識し、生きものとしてわきまえるべきものを学ぶという意味も含めた「農業の時代」であり、「農業で学ぶ」授業を通して、子どもたちの心にこの地球に生きる上での謙虚さ、同じ生きものである仲間たちに向けた優しい眼差し、そして、その学びを通して美唄の子どもたちの胸に、美唄に育ち暮らした「誇り」が湧き上がってくると信じています。
美唄市小学校農業科読本の冒頭には、「あなたが生きものであることを学ぶ農業」と題した中村桂子さんのメッセージを掲載しています。
この読本は市内の小学3年生から小学6年生の総合的な学習の「農業科」の時間で使用されます。
グリーン・ルネサンスについて(別ページへ遷移します)