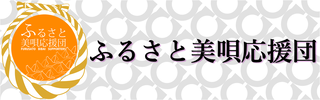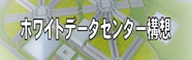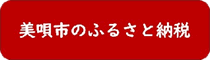本文
平成25年度第9回経営会議の概要
平成25年12月2日(月曜日)
市長会議室
1 開会
2 議事
(1)議員協議会報告案件
(以下会議資料により説明)
- 美唄市空き家等の適正管理に関する条例の概要[PDFファイル/262KB]
- 地方公営企業会計制度見直しの概要について[PDFファイル/440KB]
- 美唄市社会教育委員の定数及び任期に関する条例の一部改正素案の概要[PDFファイル/170KB]
- 美唄市消防長及び消防署長の資格を定める条例(素案)の概要[PDFファイル/203KB]
〈質疑応答〉
【保健福祉部理事】 空き家の関係の公表はどのようにするのか。
【総務部長】 命令をして、従わない時に公表する事にする。この公表の前段で意見を述べる機会を与える。
【保健福祉部長】 お金が無いから出来ないというものが沢山出て来ると思うが、そういうのはどうするのか。
【総務部長】 その辺の具体的な部分までは現状では細かく整理はしていない。
【市長】 判断は危機管理で全部判断をするのか。
【総務部長】 その前段で、庁内で会議を設ける必要があると考えている。ここでは、そこまでのものは入れておりません。
【副市長】 どういう場合に公表するか、お金があれば全部出来るけれども、そう言った低所得者も含めて、それは問われるかもしれない。
【総務部長】 なかなか公表は厳しい部分である。
【保健福祉部長】 難しいでしょうね。すぐそこの空き商店は猫が出入りしてたり、周りを全部ビニールなんかで囲っていますけれども、火でも投げられたら大変なことになる。
【総務部長】 そう言う所が、沢山ある。お金が無いから出来ないという部分も全部含めて、市の窓口の方で相談に応じて、どの様な対応を取るかになる。本当に悪質な場合に付いては、公表したいと思う。
【経済部長】 フローの流れですが、想定しているのは、本当に町の中、市街地かとおもうんですけれども、農村地域の住宅の対応の要望だとかもあるが、例えば、立ち入り調査、空き家等の情報提供があった時の話ですが、結構、農村地帯は空き家が多い、町の中は今、多分想定している事ですが、農村地域で、例えば農家の方で子供達が出入りして危ないだとかって言う事で、農家の空き家の情報提供があった時に、この条例の適用になって来るのか。例えば、そう言う情報が無い場合も空き家は結構あるんですけれど、そういうものも全市になっているので、細かな部分はどうなっているのか。
【総務部長】 対象地域は全市。
【経済部長】 全市ですよね。農家も非農家も関係ない。
【総務部長】 空き家は、人が住んでいなくても、適正に管理している建物であれば、別に危険な建物ではない。それは、そう言った状況にならないように啓発で終わります。
【経済部長】 農業委員さんの話で、離農して農家の方が居なくなり、土地がそのまま残っている場合だとか、建物も名義変更をしないまま残っている場合があるという事で、そう言う場合はどうなるのか。
【総務部長】 適正な管理をする様に所有者宛てに文書を送ったりする予定。今のところ、農村地区で調査をした結果、空き家は50軒、色々物置だとか、倉庫だとかもあるが、危険性があるというものは8軒ある。
【市民部長】 条例案の11条の代執行の関係だが、最後の所で、徴収する事が出来ると規定でまとめているが、本来は所有者が、やらなくてはならない事を代執行で安全確保をするという事だと思うが、そうすると、この費用負担というものは所有者が負担すべきだと思うんですけれども、出来る規定となると何か相手が応じなかったら市が費用負担をしなくてはならない様な気がするんだが、この辺はどうなのか。
【総務部長】 一応、法律上は行政代執行法の第2条で義務者から徴収出来るとなっている。第5条で、出来る規定から実際の費用を納期日を定め、その義務者に文書で、その納付を命ずることになる。だから、出来る規定ではあるけれども、命じなければならないという部分で事務的にはそこまでやる。ただ、実際にお金を取れるか取れないかと言う部分では、代執行を行ったとしても、相手の同意があってやるのが前提です。
【市民部長】 強制的に出来るという事でいいのか。
【総務部長】 それは、いいです。「強制的に命ずる」だから。
【市民部長】 そう言う解釈で良いのか。出来るというのは、やってもやらなくても良いという解釈で出来るのかなと思う。
【市長】 これは、全国的に各自治体でも非常に課題として出ている内容です。それで国の方も、これらの法律も含めて、何だかの措置を検討しなくてはならないという事も市長会を通じて話をして頂きますので、ですから今後、これらに対する動きがあると思いますから注意をして見て行きたいなと思っている。
【総務部長】 市が行った場合に付いては、なかなか費用の徴収と言うのが難しいので、注意をしてやらないと駄目である。先程、市長から話がありました通り、国では、空き家対策に付いて議員立法で検討をされて、今国会に出す、出さないという話を聞いていますので、新たな法律が示された段階で、またこの条例も見直しが必要になって来るものがあれば、見直しをしたいなと思う。
【教育部長】 先程、空き家299軒の内、危険性があるのが80軒と言うお話があったんですが、この80軒に付いて所有者、管理者を把握している割合と言うのは、どれ位ですか。
【総務部長】 今、手元には無いが、半分以上は確認をしていると思う。
【教育部長】 問題は、条例を作って実効性はどれ位なのか、そう言う事かと思う。
【総務部長】 そういった所に通知文をだして、管理をして下さいと、もう行っている所です。
【教育部長】 出来れば、公表だとか、代執行だとかはしたくないところなので、所有者、管理者を掴んだ上で、きちんと対応を求めていくというのが前提かなと思う。
【総務部長】 一番、困るのは所有者が判明しない事。その部分に付いては応急的な措置しか、出来ないので、そこが一番の課題になる。その辺の法的な対応が出来る様に国に対しては法律の制定ですとか、財政的な支援措置、そういったものを市長会などを通じて要望はして来ている所です。ただ、民法上なかなか難しい面があるというのは現実で所有者の解らない件数は、把握しているんですけれども手元に資料が無いんで、後ほどお配りする。
【教育部長】 はい。分かりました。
【総務部長】 他、何かございますか。公営企業の関係は宜しいですか。公営企業の部分で、この会計制度が見直されることにより、経営指標への影響と言うのが色々とあると思うが、ここで言われているのは、資金不足の部分が言われているが、他に大きな影響が出るものがあるんでしょうか。
【病院事務局長】 健全化に関わる経営指標で言えば、不良債務の部分以外で言えば、職員給与費とか色々とあるんですが、それにはあまり影響が無い。要するに、損益計算上は大して大きな影響はない。企業の経営状況が良いか、悪いかと言うのは、バランスシートでよく判断しますので、それが逆に言うとすごく、現金支出が伴わない費用が、かなり増えている、退職引当金ですとか、だからバランスシート上で言えば、ものすごく悪く見える。
【総務部長】 それで、資金不足の関係ですが、色々と経過措置もあるみたいだが、平成27年度策定までに財政健全化計画達成と言っているんですけれども、これに付いてはどうなのか。
【病院事務局長】 28年までは一応、経過措置はあります。だから、逆に言うと29年にどの位になるかと言うのが、少し悪くなる可能性がある。その、みなしの分がほとんど入って来ますので、ただ言うなれば資金不足に影響するのは流動資産。流動資産と言うと、負債です。流動負債が増えて来るかと言う事なので、率が上がって来る可能性がある。その時に不良債務があれば、率が上がるという事です。
【総務部長】 リース契約でしているものがあれば、今度は流動負債と言う形か。
【病院事務局長】 流動負債が上がるし、先程言った引当金も1年分は積むんです。退職金だとか、賞与だとか、全部積んでいかないとならない。多年度に出るものに付いては、流動負債に全部入って来るので、固定負債と、流動負債に分かれて来る。企業債の部分も多年度に償還する部分は、流動負債に入ると、固定負債ではなく流動負債に、毎年、そうやって降りて来る。固定負債がだから、そういうものがあるので流動負債が増える。「流動負債 - 流動資産」なので、当然マイナスの部分が増えて来るということで、資金不足率は悪くなる。ただ不良債務が無ければ、それは計算外。
【総務部長】 27年度決算までは影響ないという事でとらえて良い。
【病院事務局長】 28年までは、このままでいけるので影響は出ません。
【副市長】 例えば、資金不足比率は、これは今迄の様式表の出し方と、このバランスシートの変わった時と、今度は率が変わって来る。26年度からはどっちを使う事になるのか。
【病院事務局長】 それで、経過措置がある。
【副市長】 3年間は今まで通り。
【病院事務局長】 今まで通りで計算して良いです。
【副市長】 比率も今までの計算で出すということ。そうしたらあんまり細かい数字は出さない方が良い。
【病院事務局長】 そこで出て来ない。そこに抜けているのが、あと一つ言ったのは資本的収支の4条の部分が抜けている。リースの影響がある。リース会計を導入したのち、影響が出て来るので、それが抜けているものですから、今回はやめる。これは、あくまでも数字的に見たらどうなんだという比較なものですから、特別出す必要もない。
【市長】 政策会議の中でも、ここまでは出さなくても良いだろうねと言う話になりました。
【病院事務局長】 バランスシートでのイメージ図を見ても全然解んないです。
【市長】 これで、あと都市整備部の水道の方は、同じようなので良いか。
【都市整備部長】 同じ財務指標の見せ方が変わるという部分で、今言われたように、今迄借入資本金の部分が、今度は負債の方に行くと、バランスシートでは指標は変わりますけれども、経過措置によって、それに付いては同じ扱いなので、特段大きくは変わらない。
【市長】 今後に向けて、色んな財務の関係の見せ方で、資産の問題だとか、負債の問題なんかも随分とこう、やり取りをしたが、その辺の影響と言うのは大丈夫か。
【都市整備部長】 そのへんの影響ないと思う。それによって大きく変わるという事は無いです。
【病院事務局長】 先程言った、資本金の取り扱いが変わるというのは、欠損金を資本金で取り崩してしまうというのが認められた。病院の場合は、その資本剰余が何千万か、何億しかないので、三十何億の欠損金はもう消せないんで、それはやめましょうと、そういう形はあるんですけれども水道の場合は、工事負担金とか欠損金を色々と持っていますから、それで解消する事は可能かと、ただ逆に言うと起債がかなりありますので、単年度の分で債務の方で流動負債に入り、かなり比率は高い。
【都市整備部長】 今までは資本に入れていたものが、今言った下の方に計上されてしまうので、そう言う面で大きくなってしまう。今までの単純な内部指標の計算で行ってしまうと不良債務が出てしまって経過措置によって、それは今迄の出し方で出せるという事になる。
【市長】 それは、財政の指標に影響してくる問題でないの。不良債務が増えて大丈夫なのか。
【副市長】 影響は出るのか。
【都市整備部長】 この経過措置で除ければ出る。
【副市長】 それは29年度からの数値は、29年度からで理解して良いのか。
【病院事務局長】 資金不足比率を出す時だけのやり方は、この経過を除けるという事になる。
【都市整備部長】 今まで退職引当金と言うのは、みていなかったので、その部分が若干、今度は負債の方に増えていく。流動負債で1年分だけは、増えていく。
病院事務局長 経過措置は、流動負債に組むべきものを除外する。
【市長】 問題は、どういった書き方でも良いが、今うちが抱えて行く健全化の中で大きく指標が変わる様な事があると、また基本的に見直しをして、それを解消して行かないとならない訳だから、心配されるのはその辺だけだと思う。
【副市長】 市長が言ったように、新制度に変わって、病院でも水道でもどうなるんだという、悪くなるのか、良くなるのか、数字的にも。
【病院事務局長】 基本的には、さっきも言ったように見た目が悪くなる。見た目と言うのは指標上の見た目が悪くなる。後は、そんなに大きく変わらないという事。
【副市長】 だから経営健全化計画と、それで行ったら下げる内容と、今変わったことによって、どう変わるか。そう言う部分しか聞いてこられないのでないかなと思う。あとは29年度以降どうなるか、そこは29年度以降の変わらないという説明になるかも知れない。
【副市長】 パブリックコメント条令では、条例制定の場合は全部、議員協議会にかける事になっているのか。
【教育部長】 基本的には。
【副市長】 何か、要らないような気もするが、例えば、一括法で権限移譲されて条例で、きっとこれからも出て来るが。
【教育部長】 そうですね。こういう基準とか、地方で定めるものに基づいた進め方みたいなものは全部パブリックコメントをとらないと駄目と言う事です。条例で決まっている。
【総務部長】 その他、皆さんの方から何かありますか。無いようでしたら、これで経営会議を終わります。