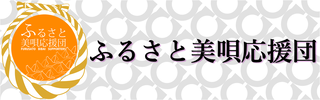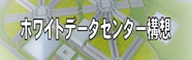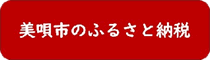本文
平成23年度第4回経営会議の概要
日時 平成24年1月27日(金曜日)午後14時20分~17時00分
場所 市役所2階 市長会議室
出席者 市長、副市長、教育長、消防長、総務部長、市民部長、保健福祉部長、商工交流部長、農政部長、都市整備部長、恵風園・恵祥園長、病院事務局長、教育部長、議会事務局長
- 開会
- 各部運営方針の進捗状況と市議会での課題と対応
- 報告案件
各部月例報告(苦情・要望、イベント結果、事故等状況、業務執行状況) - 協議案件
高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(第5期計画、H24~26)及び美唄市障がい者プラン(第3期計画、H24~26)の策定について - その他
さわやかあいさつ運動について - 閉会
1 開会
2 各部運営方針の進捗状況と市議会での課題と対応
〈関係部より資料に基づき説明:資料【PDFファイル】〉[PDFファイル/1.5MB]
〈主な意見〉
総務部
- (市長)財政健全化の4指標はどのような状況か?→(総務部長)決算見込みをとりまとめた状況でその段階では若干の黒字見込みではあるが、今冬の雪への対応により黒字は見込めなくなった状況もあるので、今後また改めて整理する。
- (市長)自主防災組織への町内会からの相談状況は?
→(総務部長)4町内会程から相談を受けている。出前講座において手法などを説明してきているが、今のところ実施に向けて手を挙げているところはない状況。 - (市長)公契約条例に関する現在までの対応状況は?
→(総務部長)庁内の入札契約制度検討委員会において勉強会をする予定であるが、既に制定済みの他市の条例を比較しながら、市にとって必要かどうか、今までの取組み方で不十分かどうか検討していきたい。
市民部
- (市長)乗合タクシー実証運行は登録制となっているが、登録していない方への対応は?
→(市民部長)実際には車を持っていたり、入院して家に住んでない方もいるので、全員登録とはならないが、町内会の代表者を通じて全戸に周知済みである。 - (副市長)地域公共交通市民バス東線の実証運行の計画ではアルテから我路のスキー場までは乗り合いタクシーだけとしていたが、地域の要望やスキー場もあることから、乗り合いタクシーに加えて、つなぎで1日3便、10人乗りの小型車で乗り継ぎできるように変更した。
- (市長)ゴミの堆肥化をする場合の収集方法などその他の協議の内容についてどのような状況か?
→(市民部長)3R推進委員会において収集方法として袋またはバケツを見せながら説明をしたところ、バケツについては衛生面などから抵抗があるということ、また生ゴミの水を切るのが大変であるというような意見があった。なお、3R推進委員30名の内、4名ほどがバケツによる堆肥化を個人的に実施している。 - (副市長)生ゴミの堆肥化実施に向けた方向性はいつごろまでに整理をするのか?
→(市民部長)遅くても9月までには堆肥化の手法、方向含めて整理したいと考えている。場所が決まれば地域との調整も必要になる。 - (副市長)実施に向けた方向性が出たら環境アセス実施に向けた補正予算も考えられるということか?
→(市民部長)はい
保健福祉部
(副市長)フッ化物洗口はどういう状況か?
→(保健福祉部長)昨年末に空知総合振興局へフッ化物洗口推進重点地区の申請をし、今年度については、薬剤をもらえるようになった。現在は水でトレーニングをしているところで、2月から薬剤を入れて実施することとなっている。
商工交流部
- (市長)市内からのHCC入学予定者の状況は?
→(商工交流部長)現在、3名。今年度の入学者は6名。 - (市長)市民ふれあいサロンの状況は?
→(商工交流部長)コアびばいには今まで通りにはできない旨話をしている。今後は、市民ふれあいサロン運営協議会のようなものを立ち上げ、そこが実施主体となり、独自に行う事業に対して市がにぎわい創出の部分で助成をするという形を考えている。 - (市長)交流人口の状況は?
→(商工交流部長)今年度、観光客の入込み客数は減っている。凧祭りがなくなったのが一つの要因。ゆ~りん館についても日帰り客が減少傾向にある。 - (市長)今後観光については、情報や魅力の発信を充実するなど入込み客数、交流人口を増やしていかないと地域の経済振興が進まないのでなんらかの対策が必要。今後美唄市の観光についてのあり方をまとめる必要がある。
- (市長)食料備蓄基地については、誘致に向け商工会議所と連携し取り組む必要がある。
- (市長)アンテナショップの今後については?
→(商工交流部長)同じ場所で継続して実施していくことを考えており、現在、販売手数料の率について調整中の段階。 - (市長)現在の場所や規模では売上額や情報発信において限界があるので、今後考えていかなくてはならない。
→(商工交流部長)来年度継続して実施していく中で検討する。 - (副市長)別の地区でも同じような直販所を実施したいという相談があった時の対応と市の窓口体制を整理する必要がある。
→(商工交流部長)来年度、現在のアンテナショップには市は人的支援だけで助成金は出さないこととしている。
→(市長)対応を統一していおかないと不公平感が生じるので総務、商工、農政含めて窓口の整理が必要。
農政部
(市長)認定農業者を増やしていくことは必要なのか?
→(農政部長)営農の中心的役割を果たすのが認定農業者であり、今後そういう積極的に取り組む農業者を増やしたいと考えているものの、国の制度が変わってきており認定農業者に対する支援制度がなくなってきており、メリットが感じられない状況となっている。今後は、国の動きを見ながら認定農業者制度については検討していく。
教育委員会
- (市長)グリーンルネッサンス事業における道職員の出向終了に伴うその後の対応は?
→(教育部長)農政課の地域おこし協力隊員や短期の臨時職員など対応を協議中。 - (市長)沖縄との交流事業が終了し、その後の動きについては何か考えているか?
→(教育長)これまでに事業成果をまとめ、検証した上、今後の事業について検討していく。 - (副市長)幼稚園教諭の給与の見直しの状況は?
→(教育長)採用時に道職員の給与形態で採用しているため見直しは困難。今後幼保一元化の中で整理をしていきたい。
消防本部
- (市長)消防の広域化は今後どうしていくのか?
→(消防長)他の自治体の考え方があるので、状況を見ながら検討していく。 - (市長)住宅火災報知機の設置率は?
→(消防長)現在67.2%
3 報告案件
(1)各部月例報告(苦情・要望、イベント結果、事故等状況、業務執行状況)
関係部より下記の項目について説明
総務部
平成23年度工事等発注状況(工事116件、業務委託12件)
市民部
平成23年度市税収納状況(平成23年12月末現在)
保健福祉部
- 平成23年度生活保護状況
- イベント等開催結果(2012びばいっ子フェスティバル)
- イベント等開催結果(東小学校区世代間交流のつどい「めだかの学校」)
農政部
平成23年度地区別修学旅行生受入状況・受入内訳表
都市整備部
平成23年度主要建設工事等進捗状況
教育委員会
空知管内高校の出願状況
病院事務局
市立美唄病院患者数(12月外来患者数 231.6人/日)
消防本部
- 救急業務出動件数(12月末現在 1,042件)
- 平成23年度火災件数(12月末現在 15件)
- イベント等開催結果(消防出初式)
主な意見
- (市長)農家への修学旅行生の受け入れについてどのような課題があるのか?
→(農政部長)受け入れ農家が伸び悩んでいる状況。受け入れ農家を増やすため研究会独自での支援、また勉強会なども実施しているが、増えていかない状況。
→(市長)細かい課題を調査し、分析する必要がある。ひとつのビジネスチャンスなので、深川、滝川など先進地の取り組みについて細かく調査する必要がある。 - (市長)美唄尚栄高校を入学希望する市内学生の状況はどうか?
→(教育部長)これまでとあまり変わらない状況であり、岩見沢の高校を優先に出願している状況。今年の市内の高校受験生の数は昨年と比べ30人少ないが、今年、尚栄高校を希望する市内の学生も30人程、昨年に比べ減少している。
いずれにしても、3間口にしたくはないので、少なくとも6名以上の確保に向け働きかけをしていきたい。
4 協議案件
(1) 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(第5期計画、H24~26)及び美唄市障がい者プラン(第3期計画、H24~26)の策定について
- 〈保健福祉部長より資料に基づき説明:資料1〉[PDFファイル/1017KB]
- 〈保健福祉部長より資料に基づき説明:資料2〉[PDFファイル/216KB]
- 2月1日から3月1日の1か月間パブリックコメントを実施。
〈主な意見〉 - (市長)税と社会保障の一体改革など国の動きとも関連してくると思われるが、その際の計画の見直しについてどのように考えているのか
→(保健福祉部長)両計画とも期間は3年となっているが、法律の見直しがあれば、計画を変更していく。計画変更に当たっては、策定委員会が進捗管理を含めて設置されているのでその中で対応していく。 - (市長)議会の対応はどうなっているのか?
→(保健福祉部長)3月定例会の時期に議会への説明を予定している。
〈協議結果〉~内容のとおりパブリックコメントを実施することで決定。
5 その他
- さわやかあいさつ運動について
〈総務部長より資料に基づき説明:資料〉[PDFファイル/280KB] - 説明した資料については庁内ランに掲載するので、併せて部内への周知をお願いする。
〈主な意見〉 - (市長)市民からの苦情もあるので、接遇の対応について研修を行うなど対応が必要。