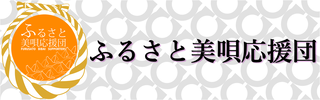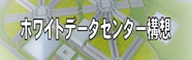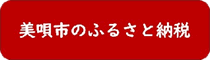本文
アライグマについて
記事ID:0000257
更新日:2020年12月16日更新
アライグマによる被害を防ぐために
アライグマとはどんな動物

北アメリカ原産で道内にはペットとして輸入されましたが気性が非常に荒いため、飼い主が捨てたり、脱走したりしたものが野生化しました。
頭胴長は40~60cm、尾長20~40cm、体重6~10kg外見はタヌキと非常に似ていますが、アライグマは眉の黒いスジや尾のしま模様があることや5本指の足あとを残すのでその違いを見分けることができます。
生息環境は、水辺の森林地帯から農耕地、市街地まで多岐にわたり、夜行性で寝場所はほとんどが家の天井裏や廃屋、物置などの建物内です。
繁殖力が強く、メスは1年で成獣となり、1回の出産で4~6頭の子を産みます。
国内では、天敵がいないため増え続けています。
なお、アライグマは外来生物法において「特定外来生物」に指定されており、北海道においても野生のアライグマの根絶を目標としており、原則、ペットとして飼うことや運搬・保管等が禁止されていますので十分ご注意願います。

アライグマの前肢(左)、後肢(中)、足跡(右)
アライグマによる被害の状況について
- 農作物被害
アライグマは雑食性です。特にトウモロコシやスイカなどが好物で、農作物を食べあらします。
トウモロコシは皮をむいて食べます
スイカは中身だけを器用に食べます - 家屋被害
屋根裏に住みつくと、ふん尿による異臭やダニが発生し不衛生な状態になります。 - 感染症や寄生虫を媒介
アライグマ狂犬病やアライグマ回虫など、人体にうつると危険な病気を持っている可能性がありますので、ふん尿には直接触れないようにしてください。
万一触れた場合は、せっけんでよく手を洗ってください。
アライグマの被害を減らすためには
- 生ごみなど餌となるものは外に出しておかない。やむを得ず、置く場合は、ふたのしっかりした丈夫なものを用いる。
- ベランダの下や屋根裏、物置など侵入されやすい場所を完全にふさぐ。
- 市では、箱わなの貸出を行っています。詳しくは農政課農政グループまでお問い合わせください。